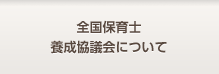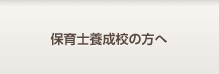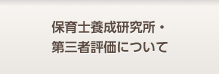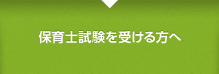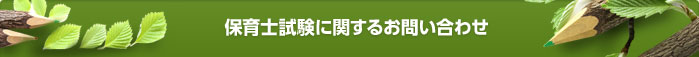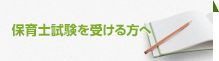特例制度とは
幼稚園教諭免許状所有者(臨時免許を除く)が対象の制度で、幼稚園等における「実務経験」により、通常の「保育の心理学」・「教育原理」・「実技試験」に加え「保育実習理論」も免除されます。
また、指定保育士養成施設における「学び」を行うことにより該当の試験科目が免除されます。
幼稚園等における「実務経験」と指定保育士養成施設における「学び」の順番(前後関係)は問いません。
詳しくはこども家庭庁HP、幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例にてご確認ください。
平成27年4月の子ども・子育て支援新制度施行後の幼保連携型認定こども園における保育教論としての実務経験を2年かつ2,880時間以上有する職員について、取得すべき8単位のうち更に2単位を修得したものとみなす特例措置が設けられました。(令和6年度末までの経過措置)
該当する方は保育士試験事務センターまでお電話にて連絡してください。
特例制度対象者
幼稚園教諭免許を取得後に、以下1~9の特例制度対象施設において「3 年以上かつ4,320 時間以上」の実務経験(児童の保護に従事)を有する方です。
- 現在就労されていない方でも、過去に幼稚園等での勤務がある方も活用することができます。
- 実務経験は複数施設における合算でも可能です。
- 幼稚園教諭免許取得前の勤務期間は認められません。
- 実務経験は、「児童の保護に従事」していることが条件です。
※ 児童の保護に従事とは、子どもの生活全般と捉えるため、主たる業務が事務の場合は該当しません。 - 対象施設に該当するかどうかは勤務された施設にお問い合わせください。
※ 特例制度の対象施設一覧については、都道府県のホームページ等で公表している場合があります。 - 受験申請の際は、施設が発行した「実務証明書」を添付していただく必要があります。
【特例制度対象施設一覧】
- 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む) - 認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)により
認定された認定こども園 - 保育所
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所 - 小規模保育事業
児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設
※平成27年度からの新規事業のため、各事業所の勤務対象期間は平成27年4月からになります。それ以前
の勤務対象期間(対象施設)になるかは、施設が所在する都道府県の保育主管課に確認してください。 - 事業所内保育事業
児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する定員6人以上の施設
※平成27年度からの新規事業のため、各事業所の勤務対象期間は平成27年4月からになります。それ以前
の勤務対象期間(対象施設)になるかは、施設が所在する都道府県の保育主管課に確認してください。 - 公立の認可外保育施設
国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする
施設(同項に規定する保育所を除く) - 離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
- 幼稚園併設型認可外保育施設
児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する施設 - 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第
0121002号)による証明書の交付を受けた施設(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)。
ただし、9は次の施設を除くことに注意してください。
※ 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位または時間単位で
不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
※ 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設
※ 平成17年以降で上記の証明書が交付されてからの勤務期間、勤務時間が対象です。上記の証明書
が交付される以前、または交付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は含まれません。
注意勤務先が対象の施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
指定保育士養成施設における「学び」とは
指定保育士養成施設において特例制度における4教科(「福祉と養護(講義 2単位)」「子ども家庭支援論(講義 2単位)」「保健と食と栄養(講義 2単位)」「乳児保育(演習 2単位)」。以下「特例教科目」と言う。)が実施されます。指定保育士養成施設が発行した「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)」(以降、「幼教専修証明書(特例)」)により下記の対応表のとおり筆記試験科目が免除されます。また、過去に指定保育士養成施設において、特例教科目ではなく、通常の養成課程の教科目(告示に定める教科目)を修得していた場合、特例教科目を修得しなくても免除になる場合があります。修得した教科目が筆記試験科目に対応するかどうかは、科目を履修した指定保育士養成施設に確認してください。
【対応表】
| 試験科目 | 修得が必要な特例教科目 | 修得が必要な養成課程の教科目※1 (告示に定める教科目) |
|
1. 社会福祉
|
A. 福祉と養護
|
① 社会福祉
|
|
2. 子ども家庭福祉
|
A. 福祉と養護
|
② 子ども家庭福祉
|
|
B. 子ども家庭支援論
|
③ 子ども家庭支援論
|
|
|
3. 子どもの保健
|
C. 保健と食と栄養※2
|
④ 子どもの保健
|
|
4. 子どもの食と栄養
|
⑤ 子どもの食と栄養
|
|
|
5. 保育原理
|
D. 乳児保育
|
⑥ 乳児保育Ⅰ
|
|
⑦ 乳児保育Ⅱ
|
||
|
B. 子ども家庭支援論
|
⑧ 子育て支援
|
|
|
6. 社会的養護
|
A. 福祉と養護
|
⑨ 社会的養護Ⅰ
|
「C.保健と食と栄養」を修得しなければなりません。
※3 上記【対応表】の赤字箇所については、科目改正に伴い名称が変更されています。
※4 科目改正に伴う経過措置等についてはこちら。
注意上記【対応表】の補足説明
1.社会福祉を免除する場合
「A.福祉と養護」 または 「① 社会福祉」を修得
2.子ども家庭福祉を免除する場合
「A.福祉と養護」及び「B.子ども家庭支援論」を修得 または
「A.福祉と養護」及び「③ 子ども家庭支援論」を修得 または
「B.相談支援」及び「② 子ども家庭福祉」を修得 または
「②子ども家庭福祉」及び「③ 子ども家庭支援論」を修得
3.子どもの保健を免除する場合
「C.保健と食と栄養」 または 「④ 子どもの保健」を修得
4.子どもの食と栄養を免除する場合
「C.保健と食と栄養」 または 「⑤ 子どもの食と栄養」を修得
5.保育原理を免除する場合
「B.子ども家庭支援論」及び「D.乳児保育」を修得 または
「B.子ども家庭支援論」及び「⑥ 乳児保育Ⅰ」及び「⑦ 乳児保育Ⅱ」を修得 または
「D.乳児保育」及び「⑧ 子育て支援」を修得 または
「⑥ 乳児保育Ⅰ」及び「⑦ 乳児保育Ⅱ」及び「⑧ 子育て支援」を修得
6.社会的養護を免除する場合
幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)を添付してしてください。
実施期間
特例制度による受験申請期間は、令和7年の試験までとなります。
ただし、令和7年3月(令和6年度)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件になります。
※令和7年3月までにどちらか一方でも満たしていない場合、免除は無効となります。
本制度に関するよくある質問とその答え
- 実務証明書の様式が欲しい。
-
こちらをプリントアウトしてお使いください。
- 昨年の受験申請時に「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」および「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)」を提出したが、今年も必要か。
-
試験科目改正の経過措置終了に伴い、平成28年以降に提出したことがある方も再度提出が必要です。 ただし、令和5年前期試験以降に提出されている方は再提出不要です。 詳しくはこちら。
- すでに免除になる科目があるが、特例教科目は4科目履修しなければならないか。
-
免除したい試験科目に対応する特例教科目のみ修得すれば、該当の試験科目が免除になります。
- 実務経験を満たしてからでないと特例教科目を履修できないのか。
-
履修できます。「実務経験」と「特例教科目の修得」どちらが先でも構いません。
- 特例制度における4教科(特例教科目)はどこで学べるのか。
-
特例制度における4教科の実施の有無や実施する教科は指定保育士養成施設により異なります。
指定保育士養成施設に直接お問い合わせするか、またはこども家庭庁のホームページ(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)にてご確認ください。 - 勤務していた施設が廃園になっている場合はどのように証明を行うのか。
-
当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合は、保育士試験事務センターにお電話にて連絡してください。 - 認可外保育施設で勤務しているが、「特例制度対象施設証明書」はどのように発行してもらい提出するのか。
-
① 施設が所在する都道府県等の保育主管課に、勤務していた施設および期間が対象であることを確認のうえ、施設・期間ともに該当する場合は「特例制度対象施設証明書」の用紙をもらう。 ②「実務証明書」を施設に作成してもらいコピーをとる。 ③ ②をもとに①の「特例制度対象施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。 ④ ②のコピーと③の原本を併せて都道府県等に提出する。 ⑤ 都道府県等より証明印が押された「特例制度対象施設証明書」が発行される。 ⑥ 受験申請時には②と⑤のそれぞれ原本を提出する。
- 特例制度の目的は何か。
-
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例ついて(こども家庭庁ホームページ)にてご確認ください。
オンライン受験申請についてのご質問
よくある質問
PDFファイルをご覧になるには、「Acrobat Reader 5.0」以上、または「Adobe Reader」などのソフトが必要です。お持ちでない方は、左記のバナーをクリックして入手してください。
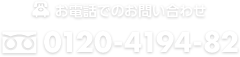
![]()
shiken@hoyokyo.or.jp
※1 受験申請期間およびその前後はすぐにお返事できない場合が
ございます。 お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
は致しかねます。やむを得ない事情によりファイルの添付を希望
する場合は、事前にご連絡ください。
保育士試験事務センター(祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30)
電話受付時間
オペレータによる電話受付は、祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30までです。それ以外の時間帯は、自動音声のみのご案内となります。※お電話がつながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。
電話受付の際のご注意事項
IP電話からはつながりませんので一般加入電話・携帯電話などをご利用ください。
または保育士試験事務センター・代表電話03-3590-5561までご照会ください。